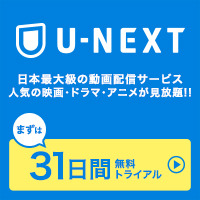2009年(平成21年)日本映画「黒部の太陽」(香取慎吾版)
黒部の太陽と言えば、石原裕次郎主演の1968年(昭和43年)の映画が有名です。
しかし、2009年にもテレビドラマで「黒部の太陽」が放映されていたのはご存じですか?
主演は、なんと! あの! 香取慎吾さんなんです。

これは、終戦まもない昭和30年代初期。
富山県東部の黒部川水系の黒部川に、黒部ダムを建設したときのお話です。
昭和31年に着工し、171人もの殉職者を出しながら7年の歳月をかけて、昭和38年にようやく完成にこぎつけました。
いくら掘っても崩れてくる軟弱な地盤、手掘りしていくしかない過酷な環境、そこに絶え間なく常に噴き出してくる4℃前後の冷たい水。
大変な苦労と犠牲の上に、たくさんの男たちが身命を投げうち坑道で奮闘する様は、この映画の見どころです。
この平成21年版の映画には、昭和43年版の映画とは違う点があります。
それは、当時の人たちが、なぜそこまでの苦労をしながらこのダムを作ったのかという説明が事細かになされていること。
当時、黒部ダム建設の経緯は第二次世界大戦後の復興期にさかのぼります。当時、関西地方は深刻な電力不足により、復興の遅れと慢性的な計画停電が続き、深刻な社会問題となっていました。
その解決には、大正時代から過酷な自然に阻まれ何度も失敗を繰り返した黒部峡谷での水力発電以外に選択肢を見い出すことができず、当時、人が行くこと自体が困難で命がけだったその秘境の地でのダムを建設するにいたったのです。

このことは当時さんざん新聞などで報道されていただけに周知の事実であり、映画ではわざわざ工事に至る経緯などを説明することもなく話が進んで行きます。
しかし、その時代を生きていない我々の世代には、わざわざそんな苦労をしてまで、なぜダムを作る必要があったのか理解できず、昭和43年版の映画ではその映画のストーリーの深部を理解することが出来ません。
平成21年版の映画では、そのような経緯が事細かに解説されており、比較的若い世代にもストーリーを理解することが出来るようになっているのが大きな特徴といえましょう。
この映画を見た後、たまたま黒部渓谷を訪れる機会がありました。
先人たちがいかに苦労してこのトンネルを掘ったか。その痕跡が黒部の谷間にも工事の遺跡を残す形で残っており、より大きな感動を得ることが出来ました。


この地で多くの若者が噴き出す冷水に苦しみ、また多量の岩石に押しつぶされる恐怖と闘いながら一本のトンネルを掘り進めたのだ。
そう考えながらトンネルを通過すると、一瞬で過ぎ去ってしまうトンネルも特別な思い出となるのです。
トンネル通過の様子を動画に収めましたが、一番前に座ればよかったと後悔。
トンネルの壁には、「破砕帯」の看板や「トンネル開通点」の看板が掲げられています。
こちらは、毎秒10トンの水が放水される観光放水。水を上向きにし、霧状に分散させることによって川底を削るのを防いでいるという。
ダムの片隅にある殉職者慰霊碑。この脇には殉職した方々のお名前の刻まれた石版もある。合掌。

この映画に、そして巨大なダムに、先人たちが培ってきたいまの日本の原点があるという事を忘れてはならないと思います。
映画を見放題で楽しむなら、動画見放題が だんぜん おススメです!!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓